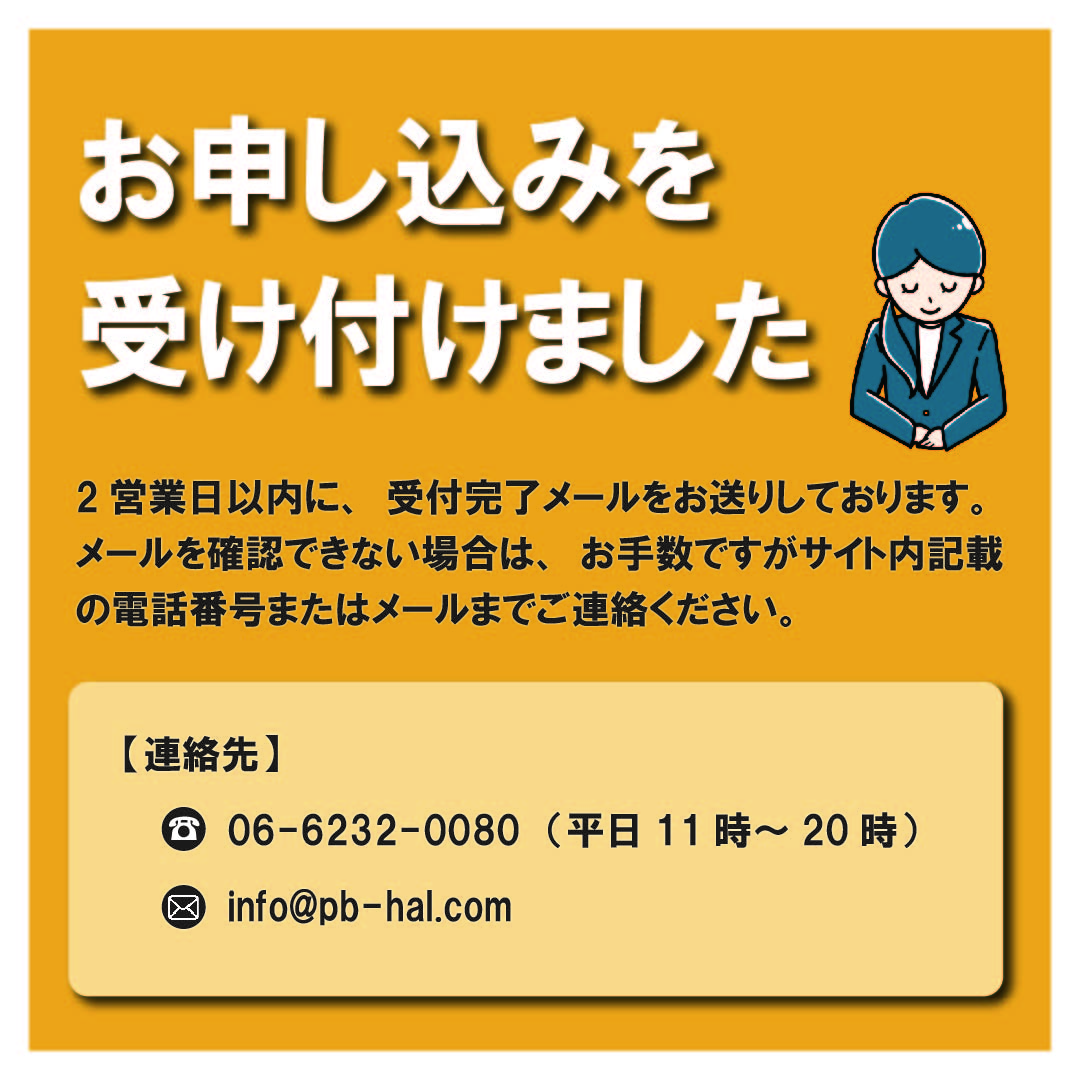Money Clinic
Newspaper
‐ 2024年12月号 ‐

教育支援拡充、それでも求められる“家庭での備え”
2025年4月から、政府は子どもが3人以上いる世帯に対して、大学授業料の実質無償化を含む大幅な教育支援を開始します。さらに2026年度からは、高等学校の就学支援金の上限額を現在の約39万6,000円から45万円へと引き上げる方針も示されました。前者は、扶養する子供が3人以上の世帯を対象に、対象の大学の授業料と入学金が無償化されます。(※私立は年間最大約70万円の支援。)所得制限がないため、対象学生の学費負担が大幅に軽減されます。
これらの施策は、少子化対策の一環として位置づけられ、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して出産・育児ができる社会の実現を目指すものとなります。特に、子どもが3人以上いる家庭にとって、大学の学費支援は非常に大きな恩恵といえるでしょう。文部科学省によれば、国公立大学の年間授業料は平均53万円程度、これが実質無償化されることで、世帯全体での支出が数百万円単位で軽減されることになります。また、高校就学支援金の増額により、私立高校の学費負担も一部軽減される見通しです。これまで、私立高校の授業料に対する支援は不十分との声もあり、引き上げによって選択の幅が広がることが期待されています。
しかし、これらの支援があったとしても、日本の教育費は依然として家庭にとって大きな負担であることに変わりはありません。例えば、文部科学省の「子どもの学習費調査」によると、幼稚園から大学卒業まで、すべて私立に通わせた場合の教育費は約2,500万円を超えるとされ、一方、すべて公立でも約1,000万円程度が必要とされています。特に私立大学への進学や、塾・習い事などの「見えない教育費」を含めると、その金額はさらに増加する見通しです。さらに、高等教育以外にも、入学金、制服代、教材費、部活動費、交通費、そして大学進学時の仕送りなど、さまざまな間接費用が発生します。こうした出費は支援制度の対象外であることが多く、家庭の負担として残り続けることとなります。加えて、教育の質や進路の多様化に伴い、塾代、スポーツの習い事、海外留学や特別支援教育、専門性の高いプログラムに通わせたいというニーズも増えてきています。これらにかかる費用はさらに高額であり、政府の支援だけでカバーできるものではありません。
このような現実を踏まえますと、教育費については、国の支援に依存するだけでなく、家庭としても早い段階から資産形成や貯蓄の計画を立てることが求められます。具体的には、貯蓄運用型の保険やつみたてNISAなどを活用し、長期的な視点で備えることが重要となってきます。子どもの未来を支えるためには、国の制度と家庭の努力が両輪となることが不可欠です。新たな支援制度の恩恵を最大限に活かしながらも、ライフプランを作成することで現実的な費用を見据え、着実な備えを検討してみてはいかがでしょうか。